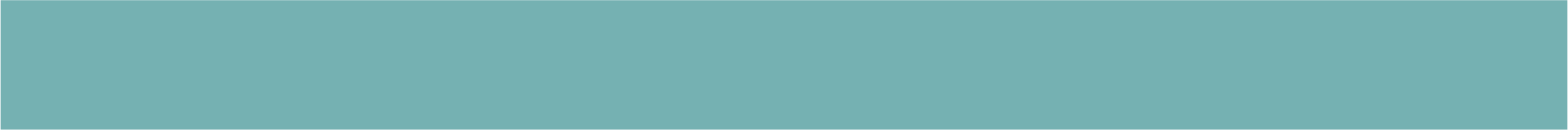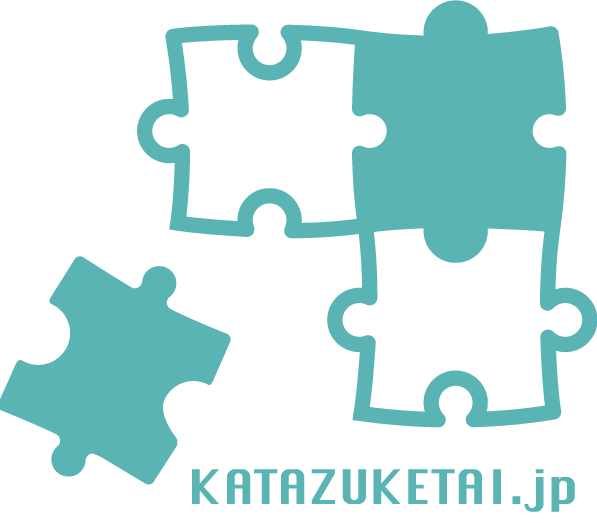疑問その2
日韓が協力して解決することは本当に不可能か
日本企業が強制連行・強制労働の被害者と和解したケースは過去にいくつもある
ドイツにならい、日韓両国と企業が参加する「財団」を設立し一括解決する方法も
「韓国側が解決せよ」では、膠着状態が続くしかない
韓国の大法院(日本の最高裁に相当)による判決が出された2018年10月30日、河野太郎外相(当時)は、すぐさま「極めて遺憾で、断じて受け入れられない」「日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すもの」と強く抗議する談話を発表しました。徴用工の損害賠償の問題は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決済み」であり、いまさら賠償の支払いなどしてしまったら日韓関係の基盤が崩壊してしまうというのです。
河野外相は上記の談話で、韓国政府に対して「適切な措置を講ずることを強く求める」としています。つまり、日本企業に大法院判決にのっとった賠償の支払いはさせない、韓国側でどうにかせよ、というのです。
以来、日韓関係は、平行線をたどりながら悪化を続けてきました。
解決の途は、本当にないのでしょうか。強制連行・強制労働の被害者を救済しようとすれば、「日韓の友好協力関係の法的基盤」が崩壊してしまうというのは、本当でしょうか。私たちは疑問に思っています。
なぜなら、戦時中の労務動員をめぐる問題で「解決」に至った事例は、過去にいくつもあるからです。しかも日本において、です。
私たちはすでに、朝鮮人戦時労務動員で強制連行・強制労働が行われた事実を日本の裁判所が認めていることを確認しました。また、日韓請求権協定でも元「徴用工」らの個人請求権自体は消滅していないことを確認しました。
一方で、元「徴用工」らがそれを裁判で救済される権利があるのかどうかという点で、日韓両国の解釈に距離があること、日本の裁判では「裁判上訴求する権能なし」として強制動員・強制労働で被害を受けた人々の訴えが棄却されてきたことも知りました。
しかし、「訴訟外の解決」、つまり裁判ではないかたちであれば、日本国内でも、いくつもの「解決」の事例があります。
たとえば、最高裁が強制動員被害者と被告企業の「和解」を促し、実際に成立した「西松建設中国人強制連行訴訟」(以下、西松訴訟)です。
被害を救済するための「和解」を促した最高裁
戦争中、労務動員されたのは朝鮮人だけではありませんでした。朝鮮と同様に日本の植民地だった台湾のほかに、中国の占領地から捕虜や農民を連行し、日本で強制労働をさせています。英米などの連合国軍の捕虜も、同様に過酷な強制労働をさせられました。
1990年代以降、これらの被害者が賠償を求めて日本で裁判を起こすようになります。そのうちの一つが、広島県で発電所の工事現場に強制連行されてきた中国人が起こした「西松訴訟」でした。この裁判は、1998年1月に広島地裁に提訴され、2007年4月に最高裁が原告の訴えを棄却して終わりました。
ちょっと長くなりますが、説明します。
日本が中国との間で締結した「日中共同声明」(1972年)には、中国は日本に対する戦争賠償の「請求を放棄する」と書かれています〈リンク〉。
最高裁は、ここでいう請求権の放棄とは、個人の賠償請求権を実体的に消滅させるのではなく、「裁判上訴求する権能」、つまり、裁判で救済される権利を失わせるにとどまる、と判断しました。
しかし、個人の賠償請求権は消滅していないのですから、加害者である企業が被害者に任意に自発的に賠償金を支払うことは法的に禁じられていないとの判断を示しました。
その上で、加害と被害の実態を踏まえてその救済の必要性を強調し、「本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」として、両者の和解を促しました。
つまり、被害者が裁判で訴える権利は確かに法的に消滅しているが、彼らの被害を救済する努力はなされるべきだということです。
これを受けて両者は和解。西松建設は強制労働について謝罪し、その証として和解金を拠出して基金を創設。被害者個人へのお金の支給や追悼碑の建立、慰霊祭の遂行などを行ってきました。
中国人強制連行事件訴訟では、このほかにも鹿島・花岡裁判(2000年11月)、三菱マテリアル訴訟(2016年6月)でも同様の和解が実現しています。
この西松訴訟における最高裁の論理は、韓国の元「徴用工」問題を解決するにあたっても当てはまるはずです。
実際、労務動員された韓国人が起こした裁判でも、被告企業と原告の間で和解が成立した事例があります。西松訴訟以前に、日鉄・釜石訴訟、日本鋼管訴訟、不二越第1次訴訟の三つで、慰霊事業の費用負担や解決金の支払い、記念碑の建立などで和解が成立しています。
このように、強制動員、強制労働の被害者と、彼らを働かせた企業の両者が直接協議することで和解に至った事例が、日本にはいくつもあるのです。
だとすれば、今回、大法院で賠償を命じられた新日鉄住金と原告の間でも、あるいは他の企業との間でも、当事者同士の同じような和解は十分に可能ではないでしょうか。
実際、新日鉄住金は、2013年7月にソウル高等法院が賠償を命じた後、敗訴判決が確定したら賠償金支払いに応じる意向を示していました。同社幹部は「確定判決を無視するのは困難」としていました(産経新聞13年8月18日付朝刊)。
「財団」方式で一括解決したドイツ政府
とは言うものの、強制的に動員され、強制労働を強いられた「徴用工」は、今回の裁判の原告だけではありません。もし、その一人一人が同様の裁判を行わなくてはならないとすれば、高齢の元「徴用工」たちにとっても、訴えられる企業にとっても負担が大きすぎます。また、当時の日本政府が行った戦時動員計画について企業だけが責任を負うのも納得いかない話です。日韓関係を優先して元「徴用工」の訴えを放置してきた韓国政府にも二次的な責任があると考える被害者もいるでしょう。
そこで、日韓両国の政府と企業が関与するかたちで「基金」あるいは「財団」をつくり、元「徴用工」、つまり労務動員され、様々な被害を受けた人々への謝罪と金銭の支払いを一括して行うという方法も考えられます。
ドイツ政府は、実際にそれを行いました。
ドイツは第2次世界大戦中、占領地から数百万人に上る多くの人々を強制動員し、強制労働をさせました。90年代後半以降、その被害者らが、フォルクスワーゲン社やBMW社などを相手にアメリカの裁判所で訴訟を起こすようになります。
これを受けてドイツ政府は、2000年に「記憶・責任・未来財団」を設立します。政府と企業が半分ずつ資金を拠出し、強制労働の被害者たちへの補償を行うものでした。財団は07年までに、およそ100カ国の約166万人の被害者に、総額43.7億ユーロ、日本円にして約5,360億円の支払いを完了しました(2016年末のレート)。
その後は、強制労働に関する歴史研究や人権に関わるプロジェクトなどを助成する活動を行っています。
日韓両国が前向きに協力して、共に強制動員被害者の救済に当たるなんて不可能だ、そんなことをすれば、「日韓の友好協力関係の基盤」が根底から崩壊してしまう――という主張に対して私たちが疑問を抱くのは、こうした日本やドイツの事例が過去にあるからです。
日本の個別企業が民事判決に従うかたちであれ、日韓両国政府が関与する財団をつくって一括して解決するかたちであれ、「解決」は決して不可能ではありません。
では、どのような選択をするのか。具体的にどう進めるのか――そこから先は、日韓両国の多くの人々が建設的な議論を通じて決めることなのだと思います。
日本企業が強制連行・強制労働の被害者と和解したケースは過去にいくつもある
ドイツにならい、日韓両国と企業が参加する「財団」を設立し一括解決する方法も
さらに知りたい方は、「徴用工」問題、少し深読みページへ
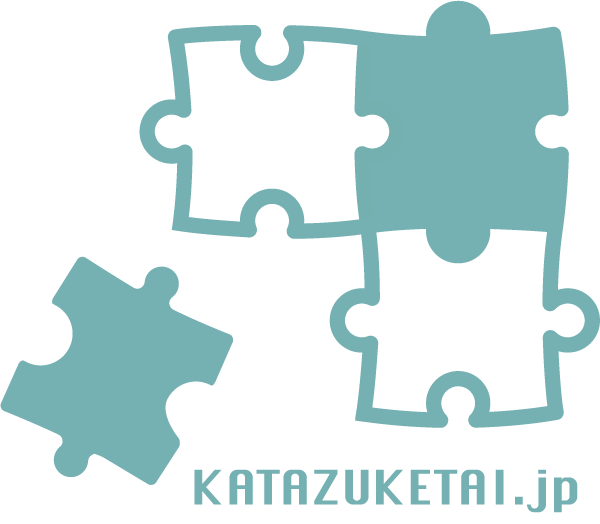
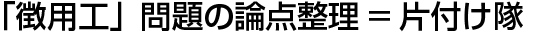
このサイトでは、「徴用工」問題=戦時強制動員問題をめぐる論議を、研究成果や判例などの「ファクト」に沿って、可能な限り交通整理してみるものです。私たちは、日本の言論空間に混じり散らばっている「言葉のガラクタ」を片付け、真摯な議論を始められる環境をつくりたいと考えています。
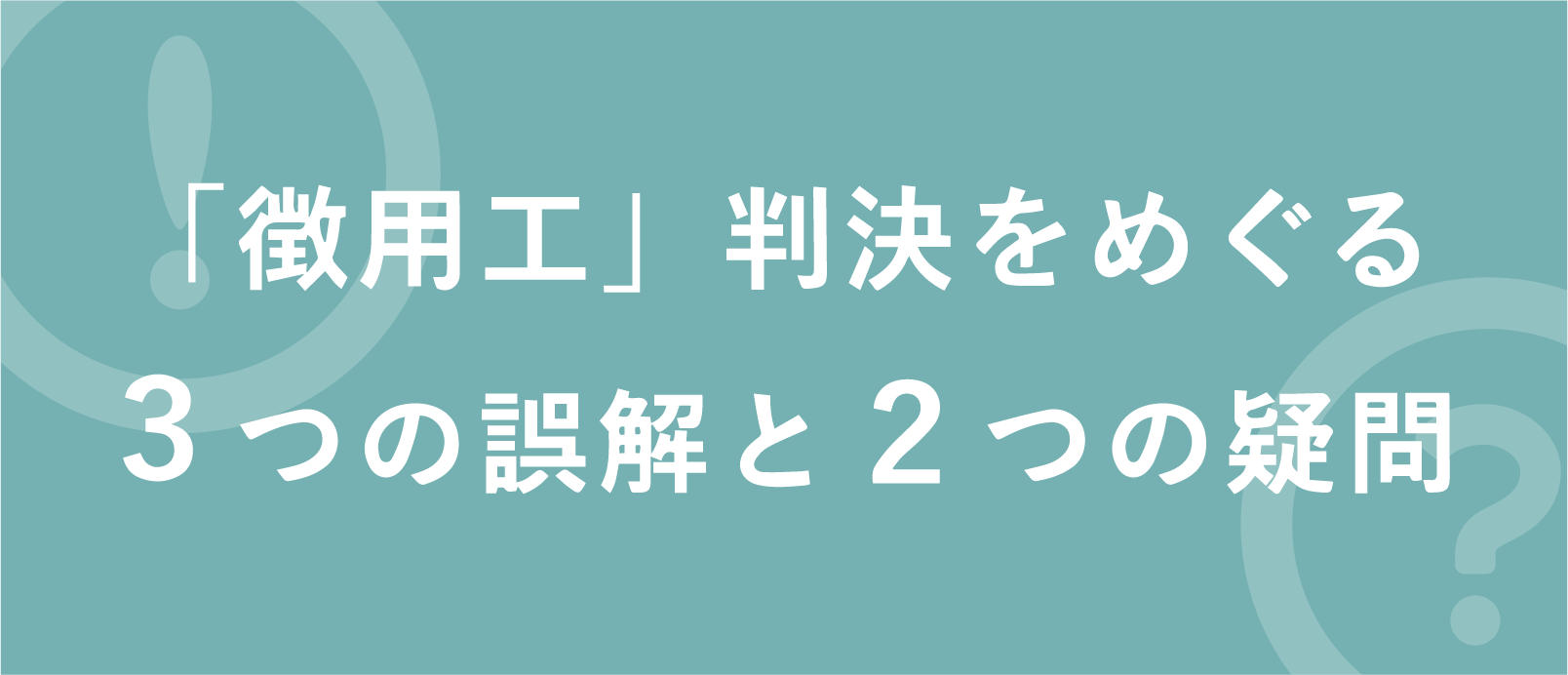
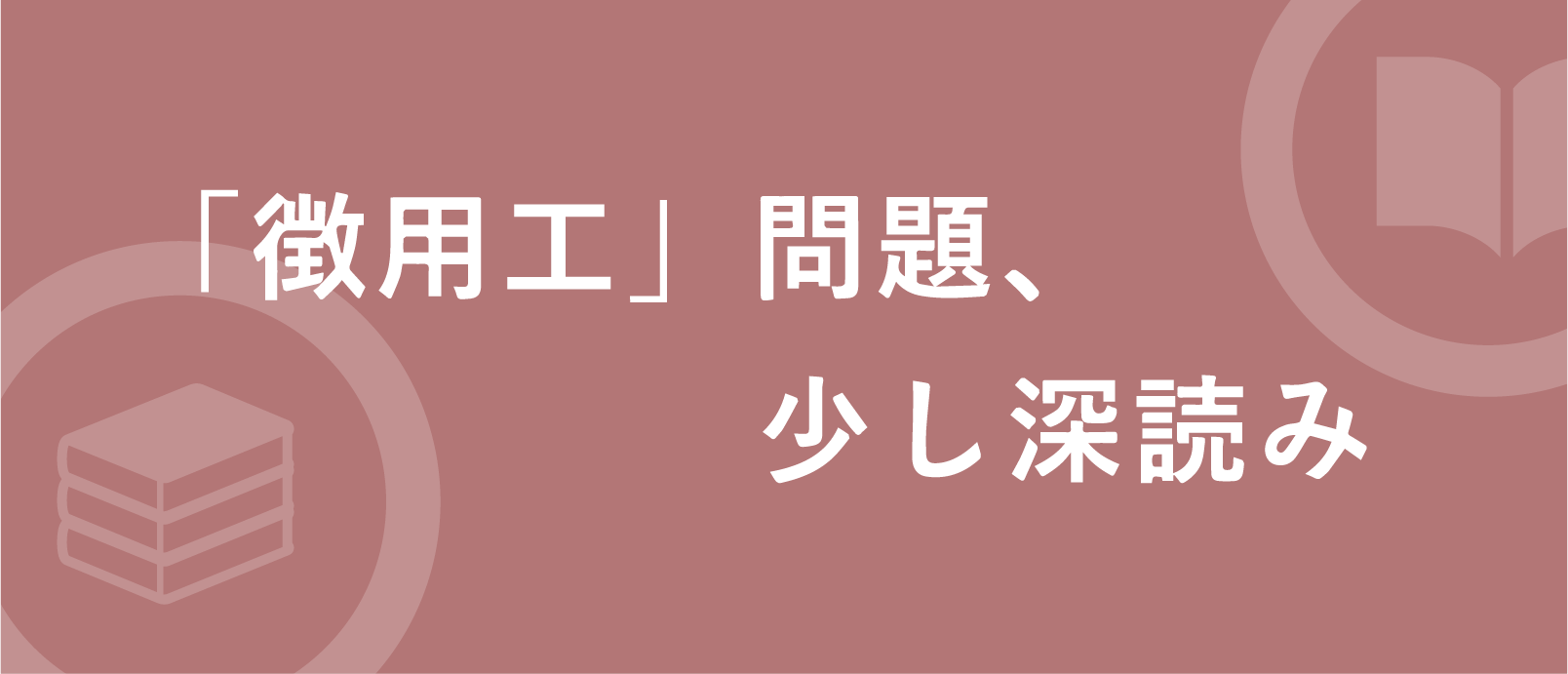
2018年10月の韓国大法院(最高裁)判決を受け、被告である日本企業の資産の「現金化」が、大きな注目を集めています。独り歩きしている「現金化」問題について、法的観点から整理してみましょう。
強制動員・強制労働を行った政府と企業が共に出資した基金を創設し、財団を通じて動員被害者に補償を行う――そうしたかたちで解決を実現したのが、第2次世界大戦時に日本の同盟国であったドイツです。
日本のメディアの中では、大法院の元徴用工勝訴判決は文在寅政権が出させたものだ、という説が広がっています。しかし、この「文在寅による判決」説には、相当な無理があります。荒唐無稽と言ってもよいかもしれません。
最新の研究では、労務動員のあり方は日本人と朝鮮人では大きく異なることが分かっています。朝鮮人の動員と、日本人の動員のどこが異なるのかを確認していきましょう。
2019年7月、韓国で『反日種族主義』という本が刊行され、話題になりました。同年11月には日本でも翻訳本が出て、出版社によれば2020年1月時点で40万部が売れているそうです。
2021年4月27日、日本政府が閣議決定した「衆議院議員馬場伸幸君提出『強制連行』『強制労働』という表現に関する質問に対する答弁書」を検証します。
「朝鮮人の労務動員は、強制労働条約が認める強制労働ではない」という日本政府の主張は、強制労働条約の間違った解釈の上に成り立っており、国際社会で認められるものではありません。なぜそう言えるのでしょうか。