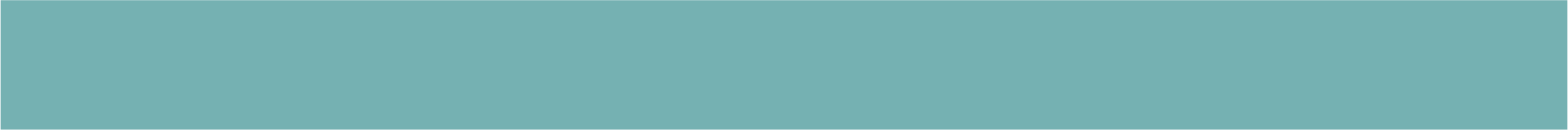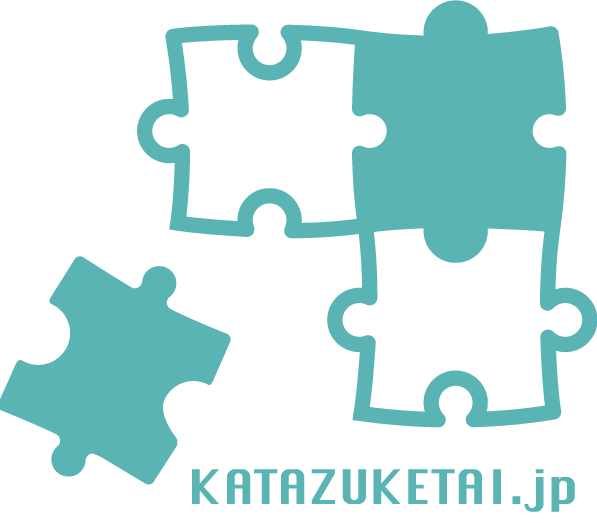◎大法院判決―被告企業資産「現金化」を考える
2018年10月の韓国大法院(最高裁)判決を受け、被告である日本企業の資産の「現金化」が、大きな注目を集めています。まるで、韓国の司法が日本企業を特別に“狙い撃ち”しているかのような誤解もあるようです。独り歩きしている「現金化」問題について、法的観点から整理してみましょう。
判決実現のための強制執行
「現金化」というのは、カネを支払うよう命じる判決を得たが、判決後もカネを払ってもらえないときに、強制執行をして、判決を実現し、カネを取り立てて、回収することをここでは言っています。
「徴用工」、強制動員の問題を少し離れて、AさんがBさんに100万円を貸した場合を考えてみましょう。早く返済するように、と交渉しても、Bさんがいつまでも自発的に返してくれないのなら、Aさんは最終的には裁判を起こすしかありません。
そして、カネを貸したことを裁判官に証明すれば、裁判官は100万円を支払え、という勝訴判決を出してくれます。判決が出た以上、被告は自発的に支払を行うべきなのですが、それをしない被告もいます。その場合、原告は、判決の実現を目指して強制執行の手続きに進むことができます。財産が見つからないなどで、強制執行がかからない場合もありますが、うまくかかればようやく、100万円がAさんの手元に戻ってくることになります。こうした仕組みは、日本でも韓国でも変わりません。
以上のことは、「徴用工」、強制動員の被害について、裁判所が加害者(被告)に損害賠償金の支払を命じた判決についても、そのままあてはまります。被告(加害者)が判決に応じない場合、原告(被害者)は判決の強制執行を行うことができるということです。それが今、話題となっている「現金化」です。「現金化」という言い方は法的用語ではないのですが、日本のメディアでは一般の人に分かりやすく、そのように表現しているのだと思います。
強制執行は被告の財産に対して行われます。財産とは、現金、預貯金、不動産だけでなく、株式や、債権、特許権などの「権利」を含みます。現金や預貯金であれば、原告は財産を差し押さえればカネを回収することができますが、不動産や株式、特許権などの現金以外の財産については、それを競り売りにかけて文字どおり「現金」化し、そのうえで、原告がカネを回収することになります。
強制執行が国をまたがることもある
ちなみに、強制執行は国をまたがって行うこともできます。ある国(たとえば韓国)の裁判所から得た判決を使って、その国とは別の国(たとえば日本やアメリカ)にある財産についても強制執行をすることができる、ということです。これも法律家にとってはふつうのことで、「徴用工」の強制動員被害に関する判決に限りません。もっとも、たとえば日本の場合は、強制執行の前に、執行判決という別の判決を日本の裁判所から得る必要があるとされています(日本・民事訴訟法118条、民事執行法22条6号、24条)。
ただ、日本の裁判所は今回の大法院判決を認めないでしょうから、この大法廷判決を使って日本にある被告の財産を強制執行するための執行判決を原告が申し立てても認めないだろうと思われます。たとえばアメリカでは事情が違うかもしれません。今回の原告が、カリフォルニア州にある被告の財産を強制執行するための執行判決をカリフォルニア州の裁判所に申し立てた場合は、同州の裁判所が執行判決を出すかどうかを判断する、ということになります。アメリカは連邦制なので、この辺りは州の裁判所が判断します。
支払の執行は大法院判決に含まれていた
新日鉄住金(当時)に対する18年10月30日の韓国・大法院判決では、新日鉄住金は被告としてカネ(損害賠償金)の支払いを裁判所から命じられています。判決が出た以上、支払をまずは自発的に行うべきなのですが、もし自発的な支払がない場合には、すでに述べてきたように、原告は判決の実現を目指して強制執行の手続きに進むことができます。
そうすると、「現金化」ということを判決から切り離して考える意味は本来はあまりありません。2018年10月30日の判決は、すでに被告に支払をする法的義務を課しているからです。判決が、被告に法的義務を課した以上、被告が自発的に支払をしない場合には、強制的にでも支払をさせて、原告を「満足」させるということは、判決がそもそも意図していたことです。
にもかかわらず、では、なぜ、いま日本では取り立てて「現金化」を問題としているのでしょうか。日本政府は、18年10月30日の大法院判決が違法、不当だ、という見解ですから、「現金化」によって、大法院判決の違法性、不当性がいよいよ現実化してしまう、違法性、不当性がもっと強力になる、としているわけです。「現金化」をせず、大法院判決を「絵に描いたモチ」にとどめておくように韓国側に警告している、という理解になります。
だとすれば、これは結局、18年10月30日の大法院判決を違法、不当とみるかどうか、という問題に帰着する、ということができるでしょう。
自発的な支払を模索すべきだった
韓国側の法的見解はもとより、日本政府の法的見解によっても、被害者の個人請求権は残っていたわけですから、05年の提訴から、18年10月30日の確定判決の前に、当事者間で和解解決をして、被告が自発的に支払をすることについては法的なハードルはなかったのでした(疑問その2参照)。そして、確定判決が出された以上は、自発的な支払をしなければ、少なくとも韓国にある財産については、強制執行を経て「現金化」に至ってしまうことは、被告にとっても自明なことだったはずです。
戦時労務動員(強制動員)への責任について被告企業が自分たちの会社、自分たちの先輩たちの来し方を真摯(しんし)に問う意味でも、自発的な解決、自発的な謝罪、自発的な支払を模索することこそが、より望ましかったといえるでしょう。
判決から2年ちかくがすぎた今も「現金化」の手続きがまだ続いているのは、原告らが被告の自発性に期待したから、というところもありました。しかし、被告の自発性は発揮されないまま、タイムリミットが近づいている状況です。
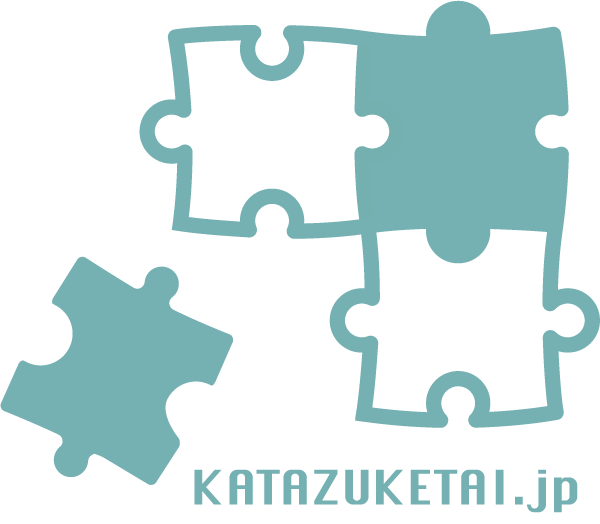
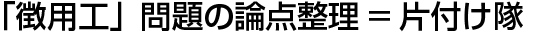
このサイトでは、「徴用工」問題=戦時強制動員問題をめぐる論議を、研究成果や判例などの「ファクト」に沿って、可能な限り交通整理してみるものです。私たちは、日本の言論空間に混じり散らばっている「言葉のガラクタ」を片付け、真摯な議論を始められる環境をつくりたいと考えています。
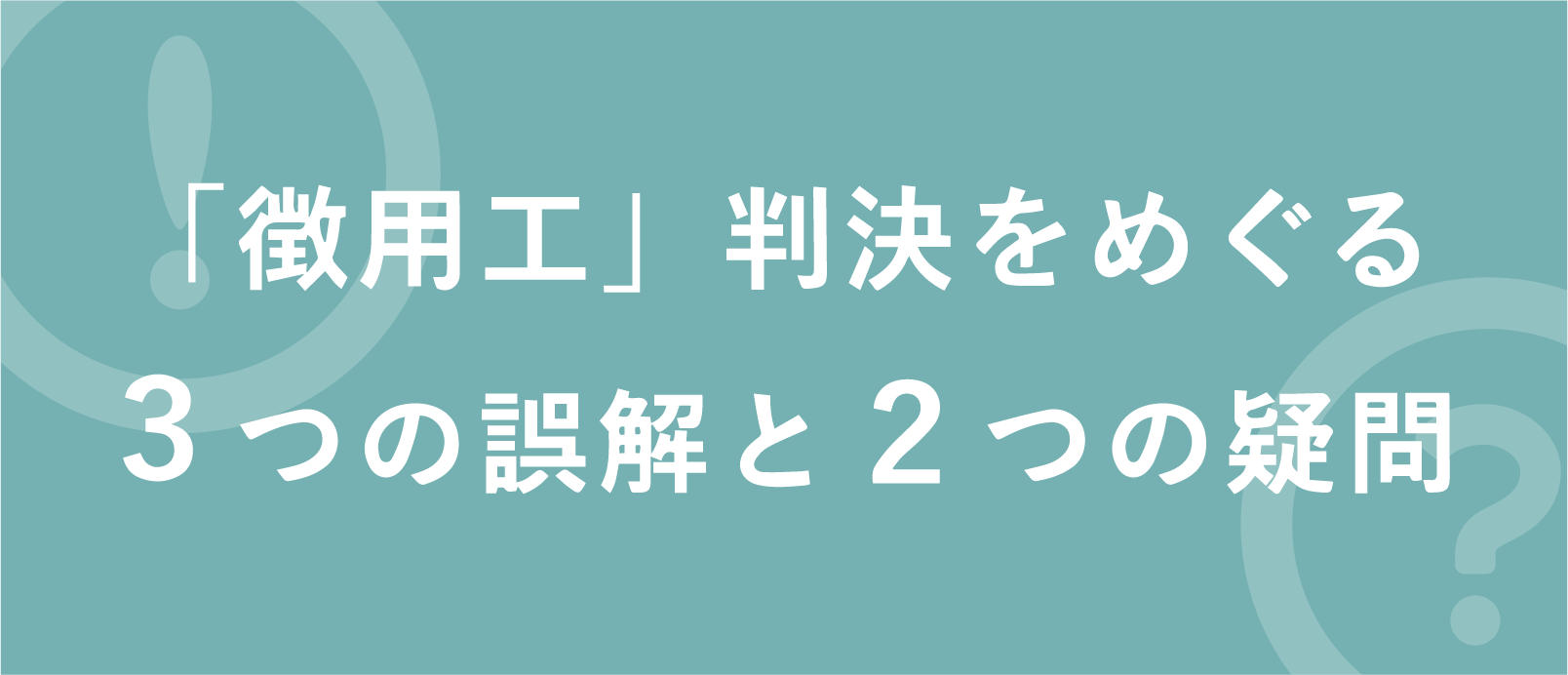
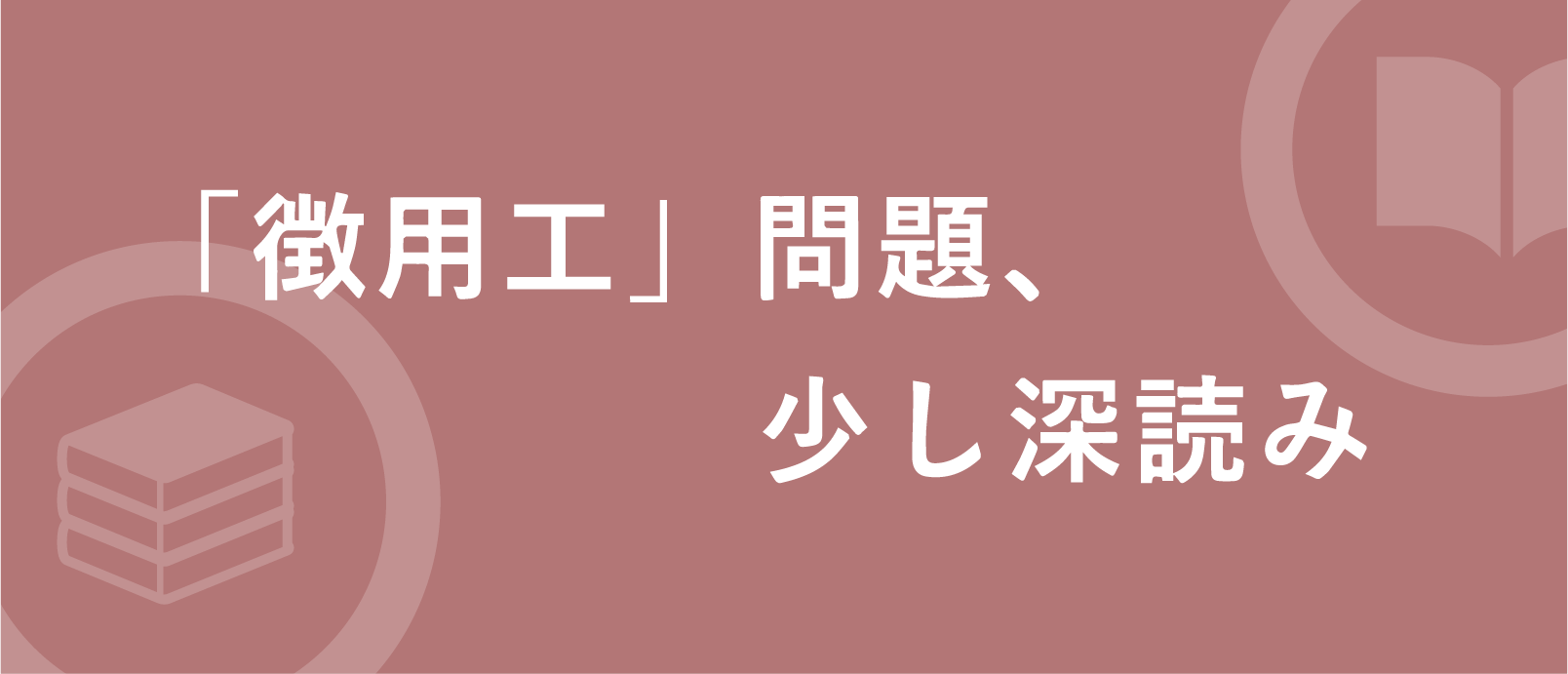
2018年10月の韓国大法院(最高裁)判決を受け、被告である日本企業の資産の「現金化」が、大きな注目を集めています。独り歩きしている「現金化」問題について、法的観点から整理してみましょう。
強制動員・強制労働を行った政府と企業が共に出資した基金を創設し、財団を通じて動員被害者に補償を行う――そうしたかたちで解決を実現したのが、第2次世界大戦時に日本の同盟国であったドイツです。
日本のメディアの中では、大法院の元徴用工勝訴判決は文在寅政権が出させたものだ、という説が広がっています。しかし、この「文在寅による判決」説には、相当な無理があります。荒唐無稽と言ってもよいかもしれません。
最新の研究では、労務動員のあり方は日本人と朝鮮人では大きく異なることが分かっています。朝鮮人の動員と、日本人の動員のどこが異なるのかを確認していきましょう。
2019年7月、韓国で『反日種族主義』という本が刊行され、話題になりました。同年11月には日本でも翻訳本が出て、出版社によれば2020年1月時点で40万部が売れているそうです。
2021年4月27日、日本政府が閣議決定した「衆議院議員馬場伸幸君提出『強制連行』『強制労働』という表現に関する質問に対する答弁書」を検証します。
「朝鮮人の労務動員は、強制労働条約が認める強制労働ではない」という日本政府の主張は、強制労働条約の間違った解釈の上に成り立っており、国際社会で認められるものではありません。なぜそう言えるのでしょうか。